ご参加いただいた皆さん、ご協力いただいた保護者・自治体・学校関係者の皆様、本当にありがとうございました。心より御礼を申し上げます。
当日の様子を、釧路校特別支援教育研究室HPで紹介しています。
こちら をご覧ください。




パラリンピックも8日目を迎え、すでに前回ロンドン大会の16個に並ぶメダルを獲得するなど、めざましい活躍を続ける日本勢だが、国別のメダルランキングでは53位と下位に沈んでいる。というのも、今のところ金メダルが取れていないことによるもので、百分の一秒単位の惜しい銀メダルがいくつもあり、何とか悲願の金メダルを、、と応援する毎日である。
前回ロンドン(金5個)の2倍のメダルを目標に乗り込んだリオ大会であったが、目標には黄信号がともっている状況となっている。
一方で、この状況について、一部関係者の間ではある程度予想(覚悟?)をしていた結果と言えるかもしれない。各国がパラリンピックを含めた障害者のスポーツ支援に力を入れるようになったなか、日本はその整備や意識改革に大きな後れを取ったのである。
これまでマスコミも含め、国民の関心は低く、競技に対する認知度も極端に低かった。そのなか、関係者は、手弁当で支援を続け、選手も海外遠征や高額な道具を含めて大きな負担のある中で努力を重ねてきたのである。
昨年から「障がい者スポーツ支援」の管轄も、それまでの厚生労働省から文科省に、そしてスポーツ庁に一元化されることになり、予算も増えては来た。しかし今回のリオには、少々遅きに失した感があるのも否めない。さらにその支援も、現在のところとても充分なものとは言えない状況にある。
またパラリンピックばかりではなく、地方を含めた障害者のスポーツ環境整備の遅れも見逃してはならない。
残りの競技での活躍を期待するとともに、今後に向けた国民全体の意識の変革が進むことを強く望んでいる。
関連記事
パラリンピックの持つ力
リオ・・パラに思う
ロンドン・パラリンピックから
スポーツの祭典:パラリンピックに想いをはせて
論文等
・アダプテッド体育・スポーツに関する国際動向 : アジア・ASAPEの取り組みとソチパラリンピック報告
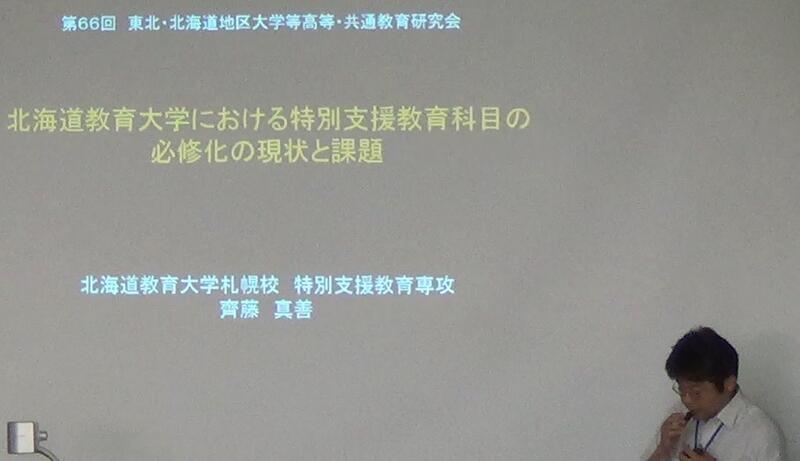
札幌校の齊藤真善先生から、8月25日(木)に、第66回東北・北海道地区大学等高等・共通教育研究会第1分科会「高等教育における人材育成-大学の国際化と人材養成プログラム-」の話題提供者として「北海道教育大学札幌校における特別支援教育関連科目の必修化の現状と課題」について報告されました。
本報告は札幌校において平成27年度から始まり、今年度より必修化された講義「特別支援教育」における受講者の「事前・事後アンケート調査」の結果及び「理解度テスト」からの分析に関する内容でした。
講義「特別支援教育」の目標は、学生達が教育フィールドで得た体験と、講義内容を融合させ、障害を抱える子どもの困り感や育ちの実際を理解し、教育現場における課題発見及び解決方法の糸口を提供することです。「特別支援教育を学ぶ必要性を感じる」というアンケートに対し、「感じる」(8割)「少し感じる」(約2割)という、ほぼ10割の学生が学ぶ必要性を感じていることからも、これからの教員にとって特別支援教育を学ぶことの重要性が見えてきます。
大学として、学生達が将来、自信をもって指導できるようにするための工夫・改善が、今後も求められるとのことでした。



2016年5月18日(水)、児童養護施設・釧路まりも学園学習支援プロジェクトが開始されました。
今年度で10年目を迎えるこの活動は、年間25回、毎週水曜日の夜18:15~19:15に学生ボランティアが児童養護施設・釧路まりも学園を訪問し、学習支援やレクリェーションを行います。
今年度は、38名の学生がボランティアとして登録しました。
5月18日は、まず体育館に参加者全員がそろい、担当する学生と子どもたちとの対面式を行いました。
その後、低学年はレクリェーション、高学年は学習から始めました。
低学年のレクリェーションでは、「だるまさんころんだ」や「いろおに」などのゲームを中心に行い、子どもたちの元気な笑い声が体育館に響きました。
高学年は、学習の冒頭に「自己紹介ビンゴ」を行い、子どもと学生が「好きな食べ物」や「趣味」などを紹介しあった後、1年間の目標を立てました。その後、学校から出されている宿題や、学生が準備した学習プリントに取り組みました。
子どもたちがいつも楽しみに待っていてくれるこのプロジェクトは、将来教師になろうとしている学生たちを励ますとともに、貴重な学びの機会となっています。
プロジェクトで大切にされている、一人ひとりの子どもたちに丁寧に寄り添い、その内面を想像してかかわる経験や、子どもの生活背景を踏まえた上での支援の構築は、今日の学校現場でも求められる事柄です。
今後も子どもたちへの支援と学生の学びがより豊かになるよう、地道に取り組んでいきたいと思います。
↓活動後の振り返りの様子

